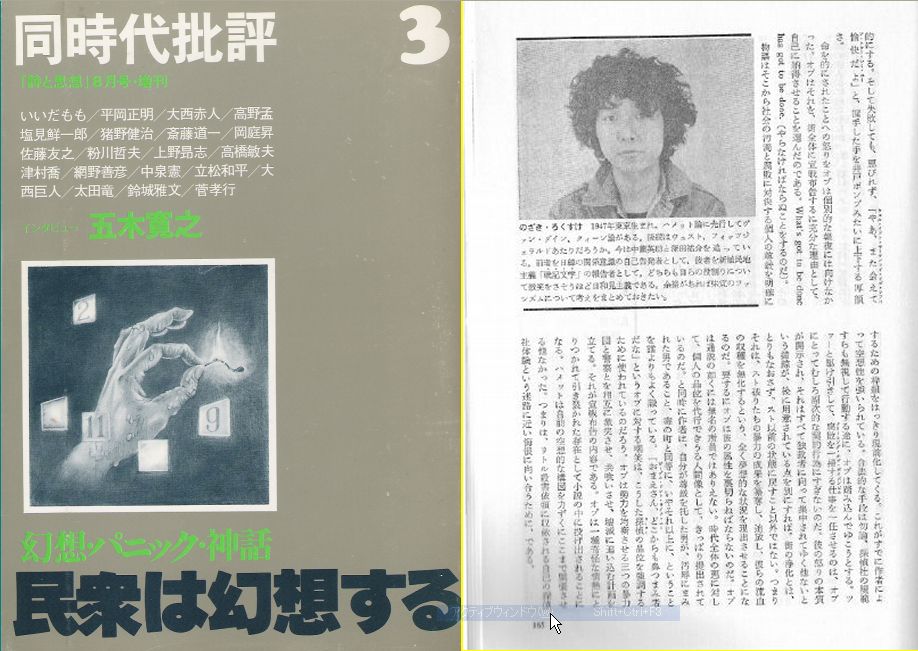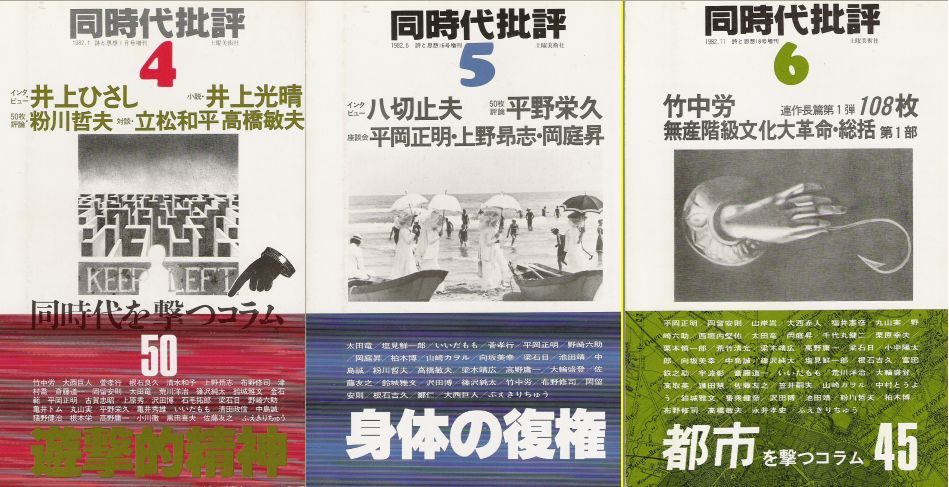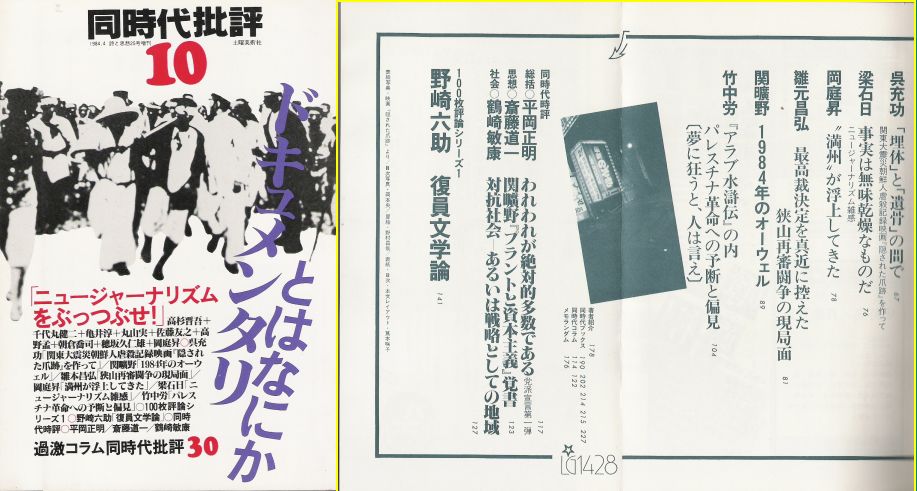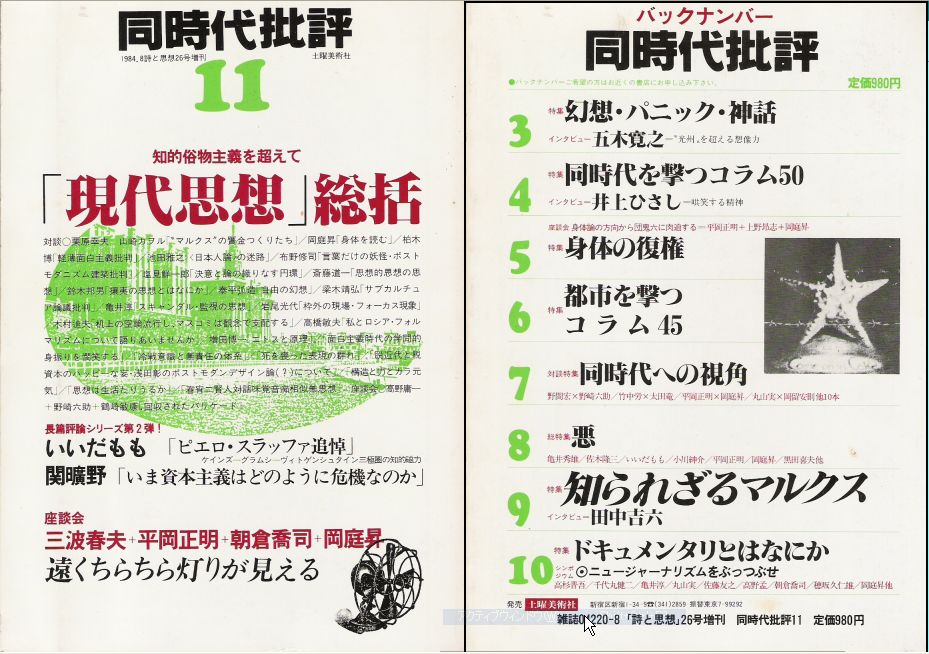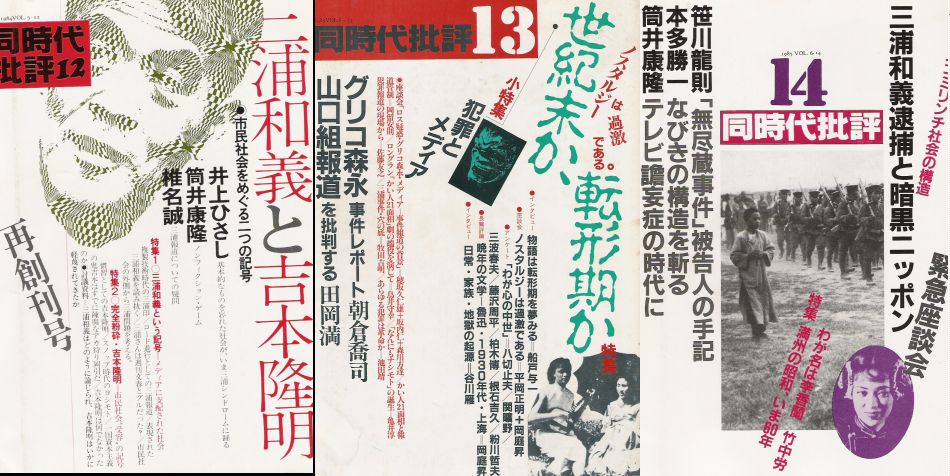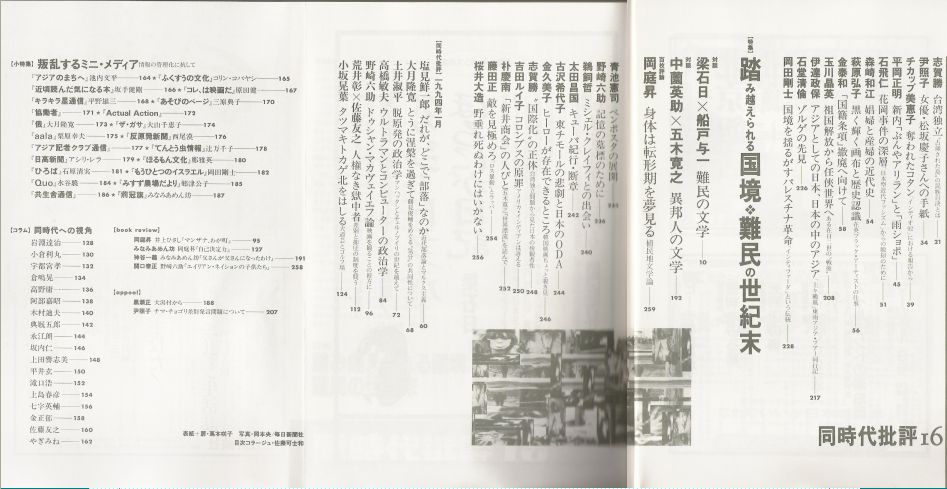|
7号 1983.5
対談と銘打っても、ほとんど内実はインタビューである。『新しい時代の文学』を中心とした野間文学の現在地点をうかがった。
最初に「あなたは学生さんですか」と訊かれたのにはまいった。先制パンチを習慣とする野間氏の対人関係のクセは野間小説ではおなじみの情景でもあるが、まさかわたしごときの若造にまで繰り出してくるとは予想しなかった。挑戦意志の80パーセントはこれで打ち砕かれたといっていい。
論題はじつに多岐にわたった。頭の回転する速度に発語の速度が伴わないという伝説的な野間話法についていくのがやっとだった。デリダ、マルクス、道元はかろうじて何とかなった。だが、デリダとマラルメになると、相槌を打つ以上のことができない。対談記録に直すと「………」である。先生は、興に乗って、先へ先へとお進みになる。言いかけたセンテンスの語尾が切れないうちに、もう次の論題に移っていかれる。魯鈍な目をしていると、この不勉強者め、と叱咤する視線に突き刺される。
記録をまとめるのも大変な作業だった。最初にテープ起こしを頼んだ人がまったくジャンル違いのキャラクターで、固有名詞をほとんど聞き取れていないという珍妙な草稿をつくってきた。一例は――「生物学は夜行性で……」。こんなふうに、意味不明の会話が延々とつづくのだ。暗号文よりひどい。夜行性とはヤコブセンのことだと気づくまでかなりの時間を要した。とにかく先生の話には言語学、分子生物学の固有名辞が頻出するのだが、これが全滅。聞き取れなかった部分は不明のままにしておけばいいのに、「夜行性」のように勝手な言葉の置き換えをしているので、余計にシュールな文章の連なりになったわけだ。
仕方がないので、全部イチから自分で起こし直した。これがまた難航したこと。対座して聞いていればついていけた野間話法がテープで聞きなおしてみると脈絡をつかまえられないところが多々あるのだ。先生の発音の微妙なところがいかにしても言語化できない。十回以上聴いても復元できない箇所が一つか二つ残り、後日、非礼であるけれど、ご本人に直接たしかめていただくことになった。おそるおそる尋ねると、先生は五分ほど沈思にこもった。ウーム。とは聞こえなかったが、内心では、この嘆息をなんどかおつきになったのであろう。そして言った。
「ここは……わからん」
親しい野間読者なら、この点々部の沈黙にこめられた混沌たる重量感に圧倒されるであろう。
「では先生、この部分はいかが処理いたしましょうか」
結局、不自然な空白が生じないように、その場で修正して、確認していただいた。
この話には、別口のオチもあって、それはテープ起こしのときのこと。話題が突然、人民戦線事件のことに移って続いていくのだ。「暗い絵」に描かれた時代の周辺だ。おかしい。わたしはそちらに話題を拡げたおぼえは全然なかった。一体どういうことかと現実感をぐらぐらと揺すぶられる想いになった。なんどもこの部分を聞きなおしてようやく了解した。テープがかぶっていたのだ。以前に録音しておいたところが消えないまま、あたかも合成されたかのようにつながっていたのだ。消えていない部分とは、岡庭さんによる野間インタビュー(これは同時代批評の1号に載っている)だ。答える人が同一なので、聞いていて自然につながっていたわけだ。それにしても、テープを通したものとはいえ、岡庭さんとわたしの声の区別が自分でつかなかったのは奇妙なことだった。
起こした原稿はまだ保管しているはずだが、このテープはどこへやってしまっただろうか。
|